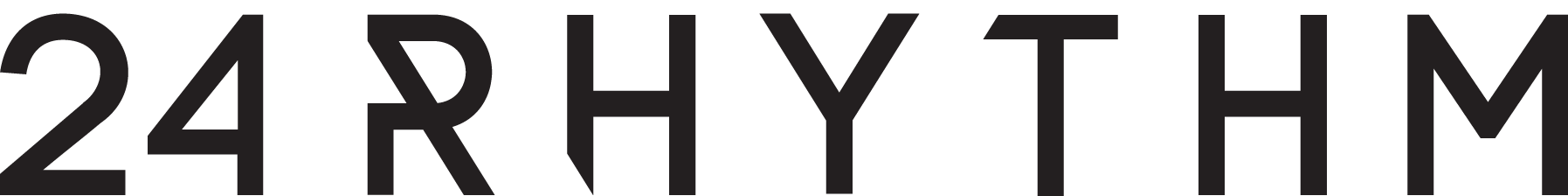2019/12/03 11:30
「24rhythm」は、しなやかに自分らしく生きる女性たちを応援しています。難病による障がいをもちながら仕事に就きジムにも通い、12月に「ホノルルマラソン10Kラン&ウォーク」にトライする高橋由香さんを紹介します。

高橋さんは「東京2020大会」のボランティアの育成研修を担う、日本財団ボランティアサポートセンター(以下ボラサポ)の職員です。週に3〜4回はジムに足を運び、体の機能改善とボディメークのために食事管理や地道なトレーニングを続けています。
彼女が進行性の神経疾患を発症したのは今から12年前。麻痺のために歩行や発話に多少の困難がありますが、今やれていることはできる限り続けたいと、仕事も運動も手放しません。そのメンタルの強さは、発症する前から大切にしているスポーツライフで培われたのかもしれません。
子どものころから体を動かすことが大好きだった高橋さんは、小学生時代はソフトボール部に所属してキャッチャーで4番の副キャプテンに。中学では陸上部、高校時代はバドミントン部に所属して、短大時代はバドミントン部でエリア大会団体優勝を果たします。卒業後に輸入車販売会社に就職した後も、サークルでバドミントンを続けていました。
バックステップがうまくできない
ところが23歳のある日、予期せぬ異変が彼女の体を襲いました。
「体育館でバドミントンの基礎打ちの練習をしていたんです。するとなんの前触れもなく足がもつれて“あれっ。バックステップがうまくできない?”と違和感を感じました。
運動好きなので最初は“ひどい筋肉痛かな?”とのんきにかまえていたんです。ところがそれから2年の間に少しづつさまざまな症状が現れました。口元に違和感があったり、舌がもつれてうまくしゃべれないこともありました。
ある日足に突っ張るような強ばりを感じて整骨院に行ってみると、『まだ若いから脳梗塞ではないと思います。でも念のために総合病院で診てもらってください』と大学病院を紹介され、いったい自分の体に何が起きているのか不安と緊張で急に胸がドキドキしだしたのを覚えています」
大学病院で検査入院をしても原因がわからず、暫定的につけられた病名は「痙性対麻痺(けいせいついまひ)」。両方の下肢が突っ張ってうまく動かせない症状が改善しないまま、1か月半ほどの入院生活が始まりました。
たとえるなら“無”の気持ち
はっきりした診断がつかないまま、病院のベッドの上でただ検査を待つだけの日々。しかし高橋さんは“特別な不安はあまりなかった”と語ります。
「入院した4人部屋はナースステーションから遠いにもかかわらず、看護士さんに笑い声が聞こえるほど仲のいい部屋でした。おかげでネガティブな気持ちになったり必要以上に落ち込むことはありませんでした。
でも無理に元気を出していたわけでもありません。わりと“無”の気持ちだったと思います。わからないことや知らないものについて考えても意味がないとも思っていました。
検査が終了して退院の日がやってきても原因は不明のまま。診察室で先生に『残念ですが、もう治る見込みはありません』と告げられて、“本当に二度と元に戻れないのか…”と、そのとき初めて涙が出ました」
このままだと人としてだめになる
「家に戻った私は会社を辞め、家事手伝いをしながら自宅療養を始めました。進行性の病気と聞いていたので家族の心労も絶えず、私自身も症状の進行に怯えていました。
でも体調の小さなアップダウンはあるものの、2年たっても症状が急激に進む徴候はみえません。
すると次第に“このままでは人としてだめになるのでは…”と思えてきました。考えた末に“そうか。また働けばいいんだ”と思いたち、思いきってハローワークに行ってみたのです」